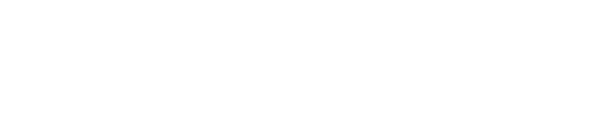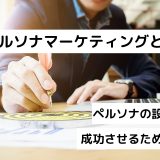- 営業だけど、うまく取引先と話せない。
- 就職活動中で営業志望だけど、雑談がどこまで必要なのか不安。
- そもそもコミュニケーションが苦手。
そんな方は多いのではないでしょうか?
アイドリングトークができれば、その悩みは解決します。
しかし、使い方を間違えると逆効果にもなり得るアイドリングトーク。
今回はそのアイドリングトークに焦点を当て、営業トークについて解説します。
 営業を成功へと導く雑談ネタ11選!雑談では避けるべきNGトークも紹介
営業を成功へと導く雑談ネタ11選!雑談では避けるべきNGトークも紹介
目次
アイドリングトークで営業成績を上げる
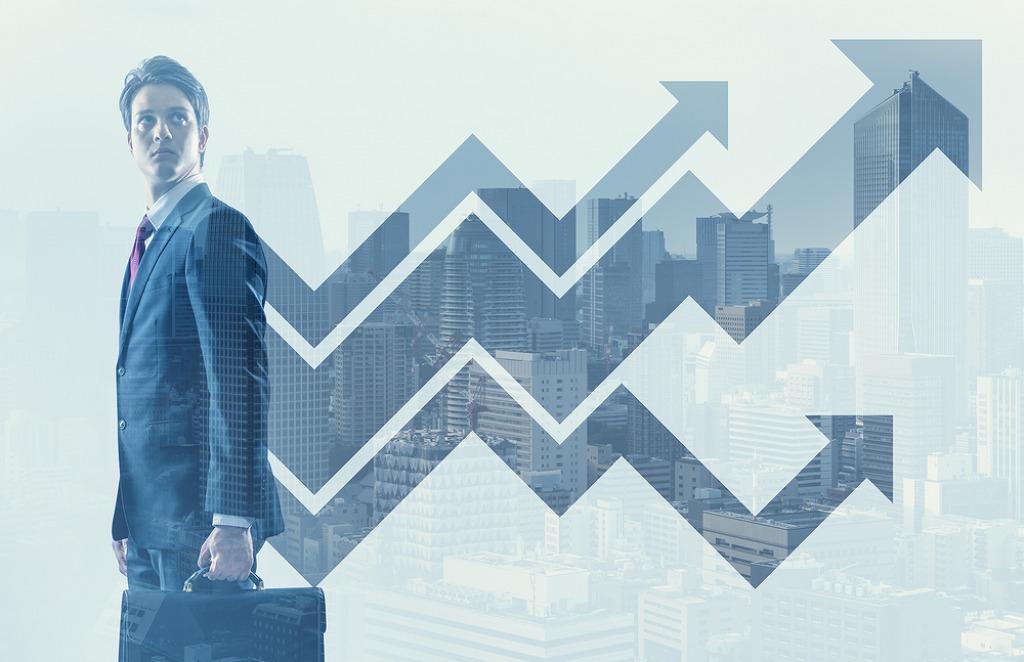
自社の製品やサービスの宣伝をする営業。
商談しかやらないという企業も、場合によってはあります。
しかし、商談のなかでは製品やサービスとは関係のない話も交えることがほとんどです。
ここからは、アイドリングトークについて紹介します。
営業で問われる雑談力「アイドリングトーク」とは
アイドリングトークというのは、本題とは関係のない雑談のことです。
世間話やアイスブレイクと言い換えることもできます。
営業では、いかにアイドリングトークをうまく挟めるかが重要です。
企業の顔といえば営業です。
営業マンがいきなり商談を始めると違和感がありますよね。
アイドリングトークを入れることで、違和感なくスムーズに商談を行うことができます。
効果的に使えば、取引先からの信頼を勝ち取り、営業成績を上げることも可能です。
 売れる営業マンの話し方を徹底解説!トーク術を習得するコツや練習方法も紹介
売れる営業マンの話し方を徹底解説!トーク術を習得するコツや練習方法も紹介
アイドリングトークのメリット3つ

アイドリングトークの効果は主に3つあります。
- 関係構築
- 情報収集
- 実力を示す
アイドリングトークはなんとなく必要だと思っていたではなく、以上のような効果があることを認識して、営業に臨むといい結果が得られます。
それぞれ順に紹介します。
①関係構築
取引先との面談を重ねるなかで、アイドリングトークを行う時間は増えていきます。
アイドリングトークに費やす時間が長くなればなる程、基本的には関係が構築され、親密度が上がります。
 できる営業マンに共通する3つの特徴|必要な行動&テクニックも解説
できる営業マンに共通する3つの特徴|必要な行動&テクニックも解説
②情報収集
アイドリングトークは、情報収集に欠かせません。
相手の価値観を知るためにも、アイドリングトークを活用しましょう。
業界の雑談にもっていけば、他社との関係を知ることも容易です。
③実力を示す
アイドリングトークのなかで自慢にならない程度で、それとなく自分の実力を示すことも可能です。
契約前であれば、契約していただいた場合の自分の実績を伝えましょう。
契約後であれば、その取引によって得られた社内での評価を伝えると効果的です。
アイドリングトークのなかで実績を示すことで、感謝を伝えると同時に、自身の実力を示すことができます。
使い方に注意!アイドリングトークのデメリット

物事には必ず例外が存在します。
「アイドリングトークはあった方がいい」のは一般的な意見ですが、これにも例外が3パターン存在します。
ここではアイドリングトークのデメリットになり得る3つのパターンについて説明します。
①アイドリングトークが苦手な取引先
取引先には口数が少なく、話すことが苦手な方もいます。
話すことが苦手な営業先の方にアイドリングトークをすると、ストレスを与えてしまいます。
その場合は、アイドリングトークは避けた方が無難です。
②早く要件が聞きたい取引先
忙しいビジネスマンには、要件だけを手短に聞きたいという方もいます。
「雑談なんていらないから、早く本題を話してくれ」と考える合理的な性格の取引先には、アイドリングトークはやめておきましょう。
営業マンが来ている時点で、目的は製品やサービスを売ることです。
③関係構築できていない取引先
会って間もない取引先は、情報がまったくない分、アイドリングトークがしやすいこともあれば、しにくいこともあります。
「何で知らないやつと雑談しないといけないんだ」
このような空気を感じたら本題から入り、アイドリングトークは後から少しずつ増やしていきましょう。
 飛び込み営業が上達する4つのコツと怒らせない営業トークテクニック
飛び込み営業が上達する4つのコツと怒らせない営業トークテクニック
パターンを見極めてアイドリングトークを活用する
以上の3パターンには、意外と多く出くわします。
無理に雑談すると逆効果になるので、本題から入るのもひとつの手です。
自然なアイドリングトークのコツ

ここまでは、アイドリングトークのメリットとデメリットを紹介しました。
次に、アイドリングトークを実施する場合のコツをお伝えします。
共通の話題をみつける
ありきたりですが、共通の話題は効果絶大です。
共通点は、多ければ多いほどいいです。
アイドリングトークをそれほど長くしなくとも、共通点があるだけで親近感を覚えます。
学ぶ姿勢を見せる
まったく共通点が見つからない場合もあります。
そのときは、自分が知らない相手の得意ジャンルに関し質問し、教えてもらう姿勢を見せましょう。
人は自分の得意分野を教えたがる傾向があるので、話がはずみます。
大切なのは学ぶ意識を持ち、学ぶ姿勢を見せることです。
タイミングを計る、タイミングを考える
一番重要なのは、アイドリングトークをするタイミングです。
アイドリングトークを最初からすることもあれば、途中や最後にする方が良いこともあります。
人によってタイミングは異なりますので、その時々で判断しましょう。
 テレアポトークスクリプトの「6ゾーン・テンプレート」!電話営業でアポ取りする例文マニュアル
テレアポトークスクリプトの「6ゾーン・テンプレート」!電話営業でアポ取りする例文マニュアル
スムーズに営業トークに入るには

アイドリングトークから、本題への入り方がわからないという方も多いでしょう。
はたから見れば無理矢理なやり方であっても、慣れると徐々に自然と本題に入ることができます。
営業初心者の方におすすめの方法は、本題と関連のあるアイドリングトークをすることです。
つまり、アイドリングトークを本題への足掛かりにするのです。
 テレアポで受付突破するテクニック!営業電話のコツとスクリプト例文
テレアポで受付突破するテクニック!営業電話のコツとスクリプト例文
アイドリングトークの例
営業をしていると、話のネタがなくなってきます。
そうならないために、アイドリングトークの具体例も確認しておきましょう。
業界ニュース
業界にもよりますが、業界ニュースが共通の話題になることがあります。
業界のニュースは毎日確認し、大きなニュースは必ずアイドリングトークで使いましょう。
得意先も興味のある話ですので、話に花が咲きます。
アイドリングトークから本題にも繋げやすいですね。
自己開示
自己開示することで、親密度は上がります。
特に、まだ関係の浅い得意先であれば、自分がどういう人間なのか、知ってもらう必要があります。
具体的には、自分の趣味や最近の失敗談が話しやすいのでおすすめです。
自己開示することで、相手も自分の話をしやすくなります。
周辺の飲食店
異動した直後に使いやすい話題です。
おすすめの飲食店を聞いた後は、次の面談までに必ず足を運びましょう。
お店での感想を伝えることで、「本当に行ったんだ」と思わせることができ、好印象です。
まとめ
今回はアイドリングトークについて、メリットやデメリット、コツ、具体例などを紹介しました。
アイドリングトークのメリットは3つです。
- 関係構築
- 情報収集
- 実力を示す
そして、デメリットになるパターンは3つです。
- アイドリングトークが苦手な取引先
- 早く要件が聞きたい取引先
- 関係構築できていない取引先
使い方に気をつける必要はあるものの、営業する上でアイドリングトークは必須のスキルです。
タイミングに注意しながら、効果的に使う方法を覚えると、自分の引き出しを増やすことができますよ。